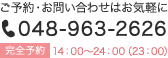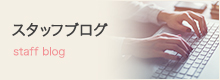概要
脳内の血管が細くなったり、血栓ができて血管が詰まってしまい発生する症状。血管が詰まると血液の流入が止まり、脳に酸素や栄養が行き渡らなくなる。その結果、脳の神経細胞が壊死してしまい、さまざまな障害が生じる。血管の詰まり方によって症状がさらに分類されており、首や脳の比較的太い血管で動脈硬化が進行し、血流が妨げられて起こる「アテローム血栓性脳梗塞」、脳の奥の方の細い血管が詰まることで起こる「ラクナ梗塞」、心臓の中にできた血栓が脳の血管に運ばれ、血管が詰まることで起こる「心原性脳塞栓」という3つの主なタイプに分けられる。
原因
脳梗塞の大きな原因としては、動脈硬化が挙げられる。動脈硬化とは、加齢に伴ってしなやかさを失い硬くなった血管に、コレステロールや脂質でドロドロになった血液が付着して血管が細くなったり、血液の流れが悪くなってしまう状態を指す。健康な血管であれば血液は留まることなく流れていくが、動脈硬化によって血管内に血流が滞る場所ができると、そこで血液が固まりやすくなり、血栓ができてしまう。こうして脳の血管内に作られた血栓や、心臓から運ばれた血栓が脳の血管をふさいでしまうことで、脳梗塞が引き起こされる。動脈硬化が起きる主な要因としては、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)がよく挙げられるが、それに加えて、高脂血症、高血圧、糖尿病、心臓病といった疾患や、肥満、喫煙、飲酒など日常の生活習慣とも密接にかかわっている。
症状
主な症状としては、左右どちらか半身の手足や顔がしびれたり動かしづらい、ふらつく(歩きづらい、めまいがする)、嘔吐する、しゃべりづらい(ろれつがまわらない、言葉が出てこない)、他人の言うことがわからない、物が見えにくかったり二重に見える、などがある。これらの症状が1つだけ出る場合と、複数出る場合とがある。突然症状が出るケースがほとんどで、場合によっては一時的に治まることもある。ただし、時間が経つと悪化することが多いので注意が必要。脳梗塞は早期に受診できるかが大きな鍵となるので、症状が出た時点で早急に医療機関へ行くことが何よりも重要。
検査・診断
脳梗塞が疑われた場合、早急に治療を開始するために、迅速な検査・診断が必要となる。CTやMRIを用いて梗塞や出血の有無を確認し、どのタイプの脳梗塞かを調べる他、頭部の血管の様子を立体画像化するMRA(磁気共鳴血管造影)で、動脈硬化が進行して細くなった血管や動脈瘤の様子を調べる。また、脳の血流の分布を画像で示し、障害が起きている部分を観察する脳血流検査や、カテーテルから造影剤を入れて検査する脳血管造影検査も行う。他に、心臓の検査(心房細動の有無を調べる心電図検査、血栓がないかを調べる心臓超音波検査)、さらに、脳梗塞のリスク要因を確かめるための血液検査も必要に応じて行われる。
治療
脳梗塞の治療は、一刻も早く始める必要がある。脳梗塞のタイプによって治療法は異なるが、基本的には点滴や飲み薬による薬物治療が中心。症状が出た直後から4.5時間以内であれば、血栓溶解薬が投与される。これは詰まった血栓を溶かす薬で、発症初期の段階に血流が戻ることで、症状の改善が期待できる。また一定の基準にあてはまれば、カテーテルを用いて血栓を取り除く血管内治療も有効。この他、急性期に投与される薬としては、脳を保護する脳保護薬や、脳のむくみを抑制する抗脳浮腫薬など。脳梗塞のタイプによって、血液の流れを促す薬剤を投与する場合もある。さらに、身体的なまひや言語障害が出ている場合は、それぞれの症状に応じてリハビリテーションを行う。再発予防のために、頸動脈内膜剥離術(CEA)や頸動脈ステント留置術(CAS)などの外科手術を行うケースもある。
予防/治療後の注意
脳梗塞を引き起こす動脈硬化の予防として、高血圧や高脂血症、糖尿病などをきちんと治療することが必要。また脳塞栓による脳梗塞については、心房細動など、不整脈の管理が重要とされる。血液が固まって血栓ができることを防ぐためには、こまめな水分補給を意識する必要がある。40代以降では、動脈硬化の状態が大半の人に見られることもあり、禁煙や過度の飲酒を避ける、適度な運動を行う、血圧を管理するなど、日頃から健康管理を意識することが大切。